変換
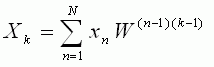
逆変換
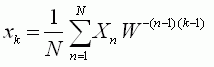
ここで、W は以下で定義され、回転子と呼ばれます。
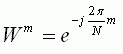
また、この回転子には以下のような重要な特性があります。
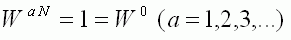
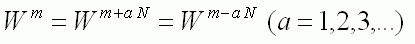
回転子は一回転をN等分しているということがわかれば、 どちらの特性もおのずとわかります。 2番目の特性は時計の針のようなもので、一回転加えても(引いても) またもとの場所にもどります。 この2番目の特性を利用すると、DFTの周期性が導けます。

さて、ここで DFT には実はいくつかの定義の仕方があります。 基本的に、変換・逆変換をあわせた演算は同じ結果になるのですが、 次のパラメータに違いがあります。
-
変換・逆変換をあわせると全体として 1/N の係数がかかりますが、
この係数を変換・逆変換に分配するやり方
(例、変換 1、逆変換 1/N や、変換 1/sqrt(N)、逆変換 1/sqrt(N) など) - 回転子の EXP の肩にのっている項の符号の取り方(+/−)
さて、回転子の符号の取り方についてですが、これもスペクトル 強度を見るだけであれば特にどちらでも問題はありません。 しかし、通常多くの技術計算では、 周波数領域においてフィルタリング、 位相特性の確認や群遅延の評価などを行います。 この場合、符号のとり方が問題となります。
結論としては、S = j ω なる置き換えを行う場合 (もしくは、群遅延=-dθ/dωにて定義する場合) はマイナスにとるということになります。
以下、10進BASICのプログラムを用いて、上記を確認します。 サンプルファイルのプログラムファイル名は dft.bas です。 キーとなる DFT 計算については、外部サブルーチン(外部副関数)にて 上記定義式をほぼそのまま記述しています。 (したがって遅いです...)
サブルーチンの内容表示 (テキストエディタによるファイル表示で、行番号はエディタによるものです)
この例では、既知の2次LPFフィルタインパルスレスポンス
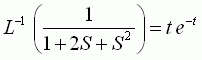
を時間軸上でサンプリングし、 これに DFT をかけることで得られるスペクトル強度および 位相特性を、ラプラス逆変換前の式から得られる値と比較しています。
入力となるインパルスレスポンスは、
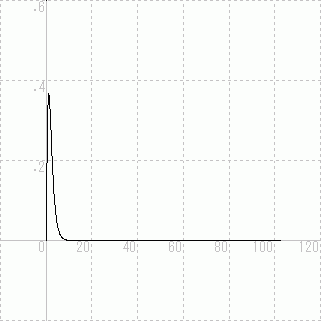
これをサンプリングして DFT をかけたスペクトル強度は、 DFT の対象性から後半半分のデータを無視すると、
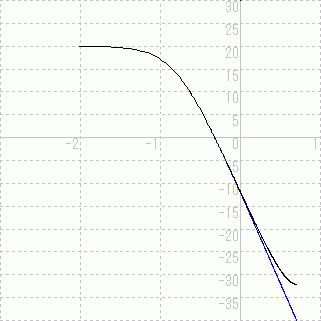
(青い線がラプラス逆変換前の式から得られた値です。)
位相特性は、
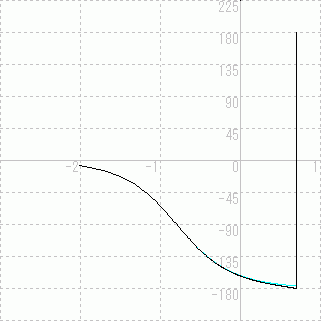
(水色がラプラス逆変換前の式から得られた値です。)
これを逆変換すると、元の波形が得られます。
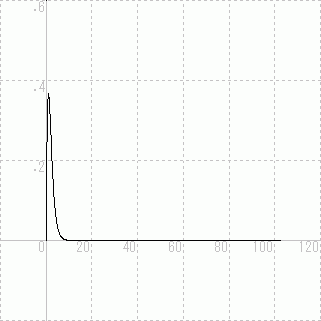
これを、DFT サブルーチン内の回転子の符号を逆にして、
exp( complex(0, 2 * pi / nx * dir * (k-1) * (n-1)) )
とプログラムを書き直して、試してみると、 位相特性のみがきれいに正負逆になります。 当然ですが、フィルタリングなどで S = jω と置いて計算した、 周波数領域での係数をこのデータにかけるとおかしな結果が得られます。 ここではあえて結果を示しませんが、 ご興味のある方は、いろいろ変更して試してみてください。
結局、回転子は位相の進行方向の定義に依存していて、あまり意識せずに 行っている、S = jω なる置き換えもまた、実は位相の進行方向を 定義しているため、両者が一致(位相遅れが負の位相になる)して いないと計算がおかしなことになる、ということになります。